ハイレゾ級放送「i-dio HQ」って、全然やる気ないこと丸わかり(1) [放送メディア]
スポンサードリンク
i-dioがハイレゾ級音質の「i-dio HQ」で番組放送開始:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
2018年8月に始まった「i-dio HQ」による放送って、技術的には、かなり興味深いことをやっていると思う。
「i-dio HQ」が採用した「HE-AAC」というコーデックは、これまで低ビットレートで比較的高音質を目指すために作られた規格だった。
通常、音楽などをデジタル化する場合、サンプリングレート(波形を検出する周期)は40KHzまたは44KHzで符号化する。
デジタル化した波形を、アナログに復元する際、サンプリングレートの半分の周波数までは、忠実に波形を再現できるということが、標本化定理という数学的原理で分かっているので、40KHzであれば人間の可聴帯域の上限である20KHzまでの再生が行なえる。
実際には、20KHz以上で発生するノイズをカットする必要があり、ハイカットフィルターを入れると、実際の上限は18~19KHzになる。サンプリングレートを44KHzにすれば、ハイカットフィルターを入れても、余裕で20KHzまでの高音を保証できるという違いがある。
例えば、radiko.jpなどでは、「HE-AAC」を使い48kbpsの低ビットレートで、128kbpsのMP3並みの音質を実現しているという。
radiko.jpでは、元の音源を、サンプリングレート22KHzのAACコーデックでエンコードする。この状態で、再生可能な周波数上限は約11KHzとなる。その代わり、ビットレートを大幅に削減することができる。radiko.jpの場合、AAC自体のビットレートは、32Kbps程度のようだ。
この状態のAACをそのまま再生すると、高音が出ないモゴモゴした変な音になるが、一応、内容は聞ける。
「HE-AAC」では、この基本のAACの上に、サンプリングレート44KHzのSBRと呼ばれる11KHz~22KHzの高域の11KHz以下との相関情報を生成し、再生時には、AACファイルに加えて、SBRから推測される高域情報を合成して、20KHzまでの音声を再生する。
MPEG-4 Part 3 - Wikipedia
さらには、「HE-AAC V2」は、左右の音声の相関からデータを圧縮するパラメトリックステレオという技術も採用されており、それらと合わせて、低容量で、より高ビットレートのMP3コーデックと同等の音質を実現している。
「i-dio HQ」は、この「HE-AAC」を、radikoなどの低ビットレートでそれなりの音質を確保するという、従来の目的とは全く違い、高音質化を目的で使用した、初めての放送だろう。
「i-dio HQ Selection」チャンネルは、とある記事によれば、320Kbpsぐらいのビットレートがあるという。
「i-dio HQ」では、AACのコーディングは、サンプリングレート48KHzで行なっているという。高域は余裕で20KHzまでの高域が出るサンプリングレートだ。
また、ビットレートを256Kbps程度確保すれば、AACだと極めて音質劣化が小さい状態でコーディングでき、CD並みの音質となるはずだ。
その上で、「i-dio HQ」では、サンプリングレート96KHzで、24KHz~48KHzのSBR情報を生成し、元のAACに付帯してHE-AACデータを生成し、放送に流してるようだ。
この方式のメリットは、まず、下位互換性の高さだ。
この「HE-AAC」の音声データを、「HE-AAC」コーデックに対応しない受信端末で再生した場合、SBR部分が無視され、サンプリングレート48KHzのAACデータとして再生される。ハイレゾには対応しないものの、これはこれで放送としては十分な高音質と言える。
ところが、これを「HE-AAC」に対応した受信端末で再生すると、SBRを解釈し、20KHz以上のハイレゾ領域の音声も併せて再生できる。これを、i-dioでは「ハイレゾ級」と呼んでいる訳だ。
「i-dio HQ」が、放送だけでなく、ネット配信でも容易にハイレゾ対応できているのは、おそらくこの「HE-AAC」を採用したからでもあるだろう。
限られる放送帯域で、高音質の放送を実現するという意味では、なかなか賢い方式だと思う。
問題は、この方式で流されている放送コンテンツの中身自体なのだが、長くなりそうなので、それについてはまた日を改めて書きたい。
関連記事:
i-dioがハイレゾ級音質の「i-dio HQ」で番組放送開始:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
スポンサードリンク
i-dioがハイレゾ級音質の「i-dio HQ」で番組放送開始:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
2018年8月に始まった「i-dio HQ」による放送って、技術的には、かなり興味深いことをやっていると思う。
「i-dio HQ」が採用した「HE-AAC」というコーデックは、これまで低ビットレートで比較的高音質を目指すために作られた規格だった。
通常、音楽などをデジタル化する場合、サンプリングレート(波形を検出する周期)は40KHzまたは44KHzで符号化する。
デジタル化した波形を、アナログに復元する際、サンプリングレートの半分の周波数までは、忠実に波形を再現できるということが、標本化定理という数学的原理で分かっているので、40KHzであれば人間の可聴帯域の上限である20KHzまでの再生が行なえる。
実際には、20KHz以上で発生するノイズをカットする必要があり、ハイカットフィルターを入れると、実際の上限は18~19KHzになる。サンプリングレートを44KHzにすれば、ハイカットフィルターを入れても、余裕で20KHzまでの高音を保証できるという違いがある。
例えば、radiko.jpなどでは、「HE-AAC」を使い48kbpsの低ビットレートで、128kbpsのMP3並みの音質を実現しているという。
radiko.jpでは、元の音源を、サンプリングレート22KHzのAACコーデックでエンコードする。この状態で、再生可能な周波数上限は約11KHzとなる。その代わり、ビットレートを大幅に削減することができる。radiko.jpの場合、AAC自体のビットレートは、32Kbps程度のようだ。
この状態のAACをそのまま再生すると、高音が出ないモゴモゴした変な音になるが、一応、内容は聞ける。
「HE-AAC」では、この基本のAACの上に、サンプリングレート44KHzのSBRと呼ばれる11KHz~22KHzの高域の11KHz以下との相関情報を生成し、再生時には、AACファイルに加えて、SBRから推測される高域情報を合成して、20KHzまでの音声を再生する。
MPEG-4 Part 3 - Wikipedia
さらには、「HE-AAC V2」は、左右の音声の相関からデータを圧縮するパラメトリックステレオという技術も採用されており、それらと合わせて、低容量で、より高ビットレートのMP3コーデックと同等の音質を実現している。
「i-dio HQ」は、この「HE-AAC」を、radikoなどの低ビットレートでそれなりの音質を確保するという、従来の目的とは全く違い、高音質化を目的で使用した、初めての放送だろう。
「i-dio HQ Selection」チャンネルは、とある記事によれば、320Kbpsぐらいのビットレートがあるという。
「i-dio HQ」では、AACのコーディングは、サンプリングレート48KHzで行なっているという。高域は余裕で20KHzまでの高域が出るサンプリングレートだ。
また、ビットレートを256Kbps程度確保すれば、AACだと極めて音質劣化が小さい状態でコーディングでき、CD並みの音質となるはずだ。
その上で、「i-dio HQ」では、サンプリングレート96KHzで、24KHz~48KHzのSBR情報を生成し、元のAACに付帯してHE-AACデータを生成し、放送に流してるようだ。
この方式のメリットは、まず、下位互換性の高さだ。
この「HE-AAC」の音声データを、「HE-AAC」コーデックに対応しない受信端末で再生した場合、SBR部分が無視され、サンプリングレート48KHzのAACデータとして再生される。ハイレゾには対応しないものの、これはこれで放送としては十分な高音質と言える。
ところが、これを「HE-AAC」に対応した受信端末で再生すると、SBRを解釈し、20KHz以上のハイレゾ領域の音声も併せて再生できる。これを、i-dioでは「ハイレゾ級」と呼んでいる訳だ。
「i-dio HQ」が、放送だけでなく、ネット配信でも容易にハイレゾ対応できているのは、おそらくこの「HE-AAC」を採用したからでもあるだろう。
限られる放送帯域で、高音質の放送を実現するという意味では、なかなか賢い方式だと思う。
問題は、この方式で流されている放送コンテンツの中身自体なのだが、長くなりそうなので、それについてはまた日を改めて書きたい。
関連記事:
i-dioがハイレゾ級音質の「i-dio HQ」で番組放送開始:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/150cda2d.b9ae6bfd.150cda2e.4d0775a6/?me_id=1312177&item_id=10329970&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgeo-mobile%2Fcabinet%2F3779%2F0683779-01.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgeo-mobile%2Fcabinet%2F3779%2F0683779-01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext) 【中古】【安心保証】 SIMフリー i-dioPhone ブラック |
にほんブログ村 | 人気ブログランキングへ |
スポンサードリンク
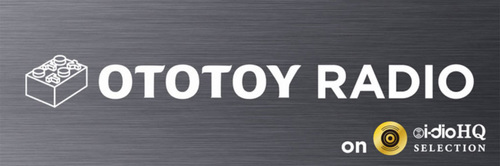




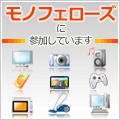



コメント 0