民放AMラジオ放送は2028年秋までに終了 [ラジオ]
スポンサードリンク
全国の民放AMラジオ、令和10年までにFMに転換目指す - SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト
AMラジオ放送を行う民間事業者47社でつくる「ワイドFM対応端末普及を目指す連絡会」が、ついに、2028年秋までに、AM放送を終了し、FMラジオ局への転換を目指すことを発表した。
これに対し、昔ながらのラジオファンからは、批判の声も多いようだ。
AMラジオ放送廃止は仕方ないんじゃないかなぁ?:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
私が、以前、AMラジオ放送廃止に対して、「やむを得ない」との意見を書いたことがあるが、今回の発表を機に、長大な批判のコメントを頂いたりもした。
そもそも、私に言っても仕方ないことなのだが、それはさておき、反対意見を書かれている方が、事実を正しく把握せずに書かれていたので、それを指摘したら、議論がかみ合わずに終了した。
これを機に、改めて、民放AMラジオ放送の終了について、私の意見を整理して書いておきたい。
まず、今回放送を終了すると発表した中には、北海道と秋田県の民放は含まれず、また、NHKは含まれていない。
北海道と秋田県については、FM局だけでは、従来のエリアをカバーすることは不可能と判断し、これからもAM波での放送を続けることを発表している。
「630億円規模縮小」 NHK計画案発表 ラジオとBS削減も=訂正・おわびあり:朝日新聞デジタル
また、NHKは、経費削減のため、2025年に、現在、2波あるAM放送を1波二削減することが決まっているが、AM放送自体を止めるということは今まで一度も発言したことはない。
NHKも国も、現時点では、災害時を考えると、全国で聴けるAM放送は必要と考えており、災害時の情報入手を危惧する方は、何も心配する必要はない。
さらに、現実を見れば、災害時の情報伝達手段の主眼は、県域FM局や、コミュニティFM局主体となっている地域が多いことも知っていて欲しい。
当たり前だが、関東のNHKのAM放送は、関東全域を対象エリアとしている。そのようなAM放送で、個々の地域事情に特化したきめ細かな災害情報を流すことなんて不可能だ。
緊急地震速報/緊急警報放送とは | 日本キャステム株式会社
地方自治台でも、FM電波に乗せる緊急地震速報/緊急警報放送に対応したFMラジオを、無料または安価で各家庭に配布して、緊急時には、自動的にラジオが立ち上がり、自治体と連携し、災害に関する放送が流れるコミュニティFM局などを自動的に選局し、災害情報を聞けるシステムを構築している自治体が増えている。
このシステムであれば、市町村ごとの細かな単位で、災害情報を発信することができ、本当の意味で市民に役に立つからだ。
こうした災害情報システムを構築している自治体では、基本、どの家でもそのラジオ局が聞けるように、地方自治体がお金を出して中継局を整備しているケースが多いし、電波でダメなら、ケーブルテレビで再配信して聴けるようにするなど、工夫をし、全市民が利用できるように考えている。
貴方も、是非一度、ご自分の住む地方自治体で、どのような災害情報システムを構築しているのか、今一度、確認してみた方がいいと思う。
「AM放送が、災害時のカギになる」なんてのは、現実を見れば、もはや妄想でしかないことが分かると思う。
さて、2028年で、北海道、秋田県以外の民放FM局は、AM放送を廃止するという。
そもそも、世界初のアナログのテレビ放送が始まったのが1932年なのに対し、世界初のラジオ放送は1920年。日本は1925年で、AM放送というのは最古の実用化された放送技術といっていい。
技術的に古いだけに、電波妨害に弱い、音質が悪い、といった根本的な弱点を抱えており、電力効率が悪い、送信設備が大掛かりになるといった、経営上にも影響がある問題点も抱えている。
FMなら、関東一円をカバーする送信設備は、東京スカイツリーの上部に、各FM局と共同で間借りする程度のコンパクトさで済むし、電力効率もいい。
それに比べると、例えばTBSラジオの戸田送信所は、東京ドームより広い敷地に、低い周波数(=長い波長)に最適な長大なアンテナ―を張る必要があり、都心にそうした広大な土地を確保しておくだけでも、固定資産税の支払いは大変だろう。
どこも経営が苦しいAM民放局としては、AM放送を廃止することが、どれだけコスト削減につながるかは分かると思う。
AMラジオ放送より後に始まったアナログテレビ放送は、2003年に地デジ放送が始まり、とっくの昔に終了したのはご存知の通り。
最近は、生まれたときからデジタル放送しか見たことがない世代も増えた。
それに対し、テレビ放送より古いAMラジオ放送という技術が、未だに現役で使われていることは、ある意味、物凄いことではある。
ただ、それだけにもう、この技術、延命に次ぐ延命でボロボロであり、限界だとも思うのだ。
よくここまで、持ちこたえてきたと思うし、エンジニアとしては、この技術を褒め称えたいと思う。
ただ、商業的には、もはや継続は難しいとは思うので、私の個人的意見として改めて書くと、「民放のAM放送については、終了もやむを得ない」と思う。
これについて、様々なご意見をお持ちの方はいると思うので、コメントは大歓迎だが、ただ、ご意見を頂く場合、しっかり報道内容を読んで、事実に基づき書いていただきたい。
関連記事:
AMラジオ放送廃止は仕方ないんじゃないかなぁ?:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
民放AMラジオ局のFM転換の日程を確認してみた:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
スポンサードリンク
全国の民放AMラジオ、令和10年までにFMに転換目指す - SankeiBiz(サンケイビズ):自分を磨く経済情報サイト
AMラジオ放送を行う民間事業者47社でつくる「ワイドFM対応端末普及を目指す連絡会」が、ついに、2028年秋までに、AM放送を終了し、FMラジオ局への転換を目指すことを発表した。
これに対し、昔ながらのラジオファンからは、批判の声も多いようだ。
AMラジオ放送廃止は仕方ないんじゃないかなぁ?:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
私が、以前、AMラジオ放送廃止に対して、「やむを得ない」との意見を書いたことがあるが、今回の発表を機に、長大な批判のコメントを頂いたりもした。
そもそも、私に言っても仕方ないことなのだが、それはさておき、反対意見を書かれている方が、事実を正しく把握せずに書かれていたので、それを指摘したら、議論がかみ合わずに終了した。
これを機に、改めて、民放AMラジオ放送の終了について、私の意見を整理して書いておきたい。
まず、今回放送を終了すると発表した中には、北海道と秋田県の民放は含まれず、また、NHKは含まれていない。
北海道と秋田県については、FM局だけでは、従来のエリアをカバーすることは不可能と判断し、これからもAM波での放送を続けることを発表している。
「630億円規模縮小」 NHK計画案発表 ラジオとBS削減も=訂正・おわびあり:朝日新聞デジタル
また、NHKは、経費削減のため、2025年に、現在、2波あるAM放送を1波二削減することが決まっているが、AM放送自体を止めるということは今まで一度も発言したことはない。
NHKも国も、現時点では、災害時を考えると、全国で聴けるAM放送は必要と考えており、災害時の情報入手を危惧する方は、何も心配する必要はない。
さらに、現実を見れば、災害時の情報伝達手段の主眼は、県域FM局や、コミュニティFM局主体となっている地域が多いことも知っていて欲しい。
当たり前だが、関東のNHKのAM放送は、関東全域を対象エリアとしている。そのようなAM放送で、個々の地域事情に特化したきめ細かな災害情報を流すことなんて不可能だ。
緊急地震速報/緊急警報放送とは | 日本キャステム株式会社
地方自治台でも、FM電波に乗せる緊急地震速報/緊急警報放送に対応したFMラジオを、無料または安価で各家庭に配布して、緊急時には、自動的にラジオが立ち上がり、自治体と連携し、災害に関する放送が流れるコミュニティFM局などを自動的に選局し、災害情報を聞けるシステムを構築している自治体が増えている。
このシステムであれば、市町村ごとの細かな単位で、災害情報を発信することができ、本当の意味で市民に役に立つからだ。
こうした災害情報システムを構築している自治体では、基本、どの家でもそのラジオ局が聞けるように、地方自治体がお金を出して中継局を整備しているケースが多いし、電波でダメなら、ケーブルテレビで再配信して聴けるようにするなど、工夫をし、全市民が利用できるように考えている。
貴方も、是非一度、ご自分の住む地方自治体で、どのような災害情報システムを構築しているのか、今一度、確認してみた方がいいと思う。
「AM放送が、災害時のカギになる」なんてのは、現実を見れば、もはや妄想でしかないことが分かると思う。
さて、2028年で、北海道、秋田県以外の民放FM局は、AM放送を廃止するという。
そもそも、世界初のアナログのテレビ放送が始まったのが1932年なのに対し、世界初のラジオ放送は1920年。日本は1925年で、AM放送というのは最古の実用化された放送技術といっていい。
技術的に古いだけに、電波妨害に弱い、音質が悪い、といった根本的な弱点を抱えており、電力効率が悪い、送信設備が大掛かりになるといった、経営上にも影響がある問題点も抱えている。
FMなら、関東一円をカバーする送信設備は、東京スカイツリーの上部に、各FM局と共同で間借りする程度のコンパクトさで済むし、電力効率もいい。
それに比べると、例えばTBSラジオの戸田送信所は、東京ドームより広い敷地に、低い周波数(=長い波長)に最適な長大なアンテナ―を張る必要があり、都心にそうした広大な土地を確保しておくだけでも、固定資産税の支払いは大変だろう。
どこも経営が苦しいAM民放局としては、AM放送を廃止することが、どれだけコスト削減につながるかは分かると思う。
AMラジオ放送より後に始まったアナログテレビ放送は、2003年に地デジ放送が始まり、とっくの昔に終了したのはご存知の通り。
最近は、生まれたときからデジタル放送しか見たことがない世代も増えた。
それに対し、テレビ放送より古いAMラジオ放送という技術が、未だに現役で使われていることは、ある意味、物凄いことではある。
ただ、それだけにもう、この技術、延命に次ぐ延命でボロボロであり、限界だとも思うのだ。
よくここまで、持ちこたえてきたと思うし、エンジニアとしては、この技術を褒め称えたいと思う。
ただ、商業的には、もはや継続は難しいとは思うので、私の個人的意見として改めて書くと、「民放のAM放送については、終了もやむを得ない」と思う。
これについて、様々なご意見をお持ちの方はいると思うので、コメントは大歓迎だが、ただ、ご意見を頂く場合、しっかり報道内容を読んで、事実に基づき書いていただきたい。
関連記事:
AMラジオ放送廃止は仕方ないんじゃないかなぁ?:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
民放AMラジオ局のFM転換の日程を確認してみた:コンテンツって言い方、嫌いだけど:So-netブログ
にほんブログ村 | 人気ブログランキングへ |
スポンサードリンク

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f8337e.cb31a7f0.08f4f1bd.c6df19a2/?me_id=1213310&item_id=19425045&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1056%2F9784866731056.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1056%2F9784866731056.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f8337e.cb31a7f0.08f4f1bd.c6df19a2/?me_id=1213310&item_id=19503596&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0498%2F4910015250498.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0498%2F4910015250498.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)




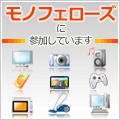



NHKの方は「AMを第1放送に一本化することを検討するように」と経営委員会が勧告したそうですね。NHKは今の総務大臣が経営のスリム化を求めているという事情があるので民放が抱えている事情と違う部分があるかもしれませんが、これから10年の間にAMが立たされる事情はかなり動くかもしれませんね。
by 関東のラジオ聴き (2021-07-06 10:19)
関東のラジオ聴きさん、こんにちは。 NHKラジオの一本化はそれはそれで大変そうですね。 ただ、大半の教育コンテンツは、アプリのオンデマンド配信とか、雑誌+DVDのような形の方が、はるかに効率的。今時、難聴エリアで、聴けても雑音だらけのAMを録音して聞いている人が、どれだけいるのか?
そう考えると、おのずと道は明らかだと思います。
by naniwa48 (2021-07-06 12:44)